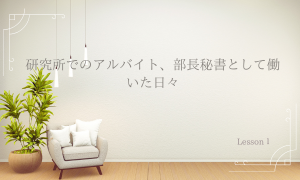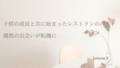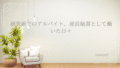研究所でのアルバイト、部長秘書として働いた日々
採用の決め手は「きちんと感」と職場からの近さ
何とか採用になりました
そんなこんなで、色々と失敗もありましたが、最終的に無事採用していただくことができました。
私の採用には研究所の方々の間でも少し不安があったそうです。ただし、採用の主な目的は、あくまでアルバイトとして、比較的スキルを必要としない雑務を任せる人材の確保だったとのこと。
具体的には、書類整理や片付け、データ入力などの事務補助的な業務が中心。
面接を通して、主婦としてきちんと生活していそうな雰囲気や、職場から自宅が近いこと。(経費的に交通費がかからない(笑))
「この人なら細かい雑務も丁寧にこなしてくれそう」と判断していただいたようです。
最初から高度なスキルを求められていたわけではなく、生活力や日々の丁寧さが評価された結果だったと後に知ることになりました。
秘書兼事務スタッフとしての仕事内容
業務内容
研究所でのアルバイトは、書類の整理、データの入力が主な業務でしたが、三ヶ月を過ぎる頃には、部長秘書兼事務補助というポジションも加わりました。この主な業務は、部長のスケジュール管理や来客対応、電話・メール応対などの秘書業務に加え、研究所全体の予算執行に関わる事務処理や資料作成といったバックオフィスの業務も含まれていました。
スケジュール管理と来客対応で磨かれた調整力
日々変動する部長のスケジュールを管理しながら、社外とのアポイント調整や会議の準備、来客のアテンドなどを行いました。これまで経験したことのないスピード感と調整力が求められましたが「先回りして準備する」ことの大切さを実感し、自然と段取り力やタイムマネジメントのスキルが身についていきました。
事務処理と予算管理で鍛えられた正確性と学び直しの日々
秘書業務では、スケジュール調整や来客対応など時間管理の面で早く慣れることができましたが、もう一つの大きな仕事である「研究所の予算管理」は、私にとって大きな壁でした。過去に触れたことがない業務であり、金額や期日、申請の正確性が求められる世界。責任の重さを痛感しました。職業訓練校で一度学んだExcelの操作も、9年のブランクがあるとほぼ忘れてしまっていて、初歩的な関数すら思い出すのに時間がかかりました。
最初に作成した予算表は、見づらく分かりにくいものばかり。部長に確認していただいても「これはちょっと…上には出せないね」と指摘されることも多く、心が折れそうになった日もあります。 けれど、そこであきらめずに「自分の強みにするチャンス」ととらえて、もう一度Excelを一から学び直すことにしました。
使いこなせるようになった関数は、SUM(合計)、AVERAGE(平均)、RANK(順位付け)、VLOOKUP(検索とデータ連携)など。単なる表作成だけでなく、「いかに見やすく、わかりやすく伝えるか」を考えるようになりました。色分けや強調、無駄な罫線の削除など、視認性を高める工夫も取り入れながら、部長や同僚がすぐに理解できる資料作成を意識しました。また、予算の収支をもとに「これは今月買えません」「来月以降に回しましょう」「補正予算を申請すれば対応できます」といった具体的な助言ができるようになったことは、自分の成長を実感できた瞬間でもあります。失敗の連続でしたが、その中で少しずつ信頼を得て、「これは任せるよ」と言ってもらえるようになった時、自分の努力が評価されたようで本当に嬉しかったのを覚えています。
再就職を目指す方へ:ブランクがあっても一歩ずつ前へ
もし今、過去のブランクやスキル不足に不安を感じている方がいたら、私は「大丈夫、できるようになります」とお伝えしたいです。
失敗しても、諦めずに取り組めば必ず道は開けます。
私自身、長い専業主婦生活によりPCが苦手となっていて、一般的な事務経験もなかったところからスタートしました。
でも、小さな成功と小さな信頼の積み重ねが、次のチャンスにつながっていったのです。
最初の一歩が怖いときは、「家から近い職場」でも、「少しの時間だけの勤務」でもいいんです。 自分の生活や家族とのバランスを大切にしながら、できる範囲で一歩踏み出してみてください。きっと、その先に新しい可能性が待っているはずです。
信頼される仕事の姿勢が評価された瞬間
小さなきっかけ
研究所のスタッフは皆さん親切で、最初は緊張していた私にも丁寧に仕事を教えてくださいました。そうした環境の中で、私は「頼まれたことをそのままやる」のではなく、常に「その先に起こりうること」を想定して仕事に取り組むことを心がけていました。
ある日、部長から「この封筒をそのまま宅急便で送っておいて」と頼まれた際のことです。
封筒を上から触ると、その荷物には割れ物が含まれていることは何となく気づきました。、私は「もし破損していたら?」「もしクレームになったら?」と、思い、一度包みを開け、破損がないか丁寧に確認したうえで、より頑丈に梱包し直し、「割れ物注意」などの注意喚起も明記。 さらに、発送前の状態を記録として写真に残しておきました。
後日、その荷物が破損した状態で届いたことが発覚し、相手先から「最初から壊れたものを送ったのでは?」といった疑いの連絡が入りました。部長からも強い口調で確認を求められました。しかし発送前の状態、梱包の様子、「割れ物」ラベル、破損がなかった中身の状態。それらを一つひとつ丁寧に説明すると、部長は明らかに態度を和らげ、最終的には「そこまでやってくれていたんだね。ありがとう」と言ってくださいました。
そのほんの小さな一手間が「信頼できる人」と認めてもらえる大きなきっかけとなりました。
再就職において、派手な成果よりも「地味だけど確実な仕事」が、職場での信頼構築に直結するという実感を得た出来事でした。