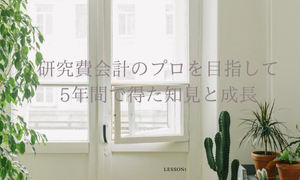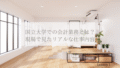研究費会計のプロを目指して:5年間で得た知見と成長
振返り
大学の会計部署に配属されてからの毎日は、想像以上に忙しく、責任の重いものでした。ですがその分、日々の積み重ねが確実に自分の力になっていることを感じる職場でもありました。ここでは、私が会計業務の現場でどのように成長していったのかを振り返ります。
あの頃より「まし」だから、踏ん張れた
入職して最初の1年間は、本当に必死でした。毎日が手探りで、正直「辞めたい」と思う瞬間もありました。それでも続けてこられたのは、OL時代の厳しい経験があったから。
「OL時代のあの辛さに比べたら、今の方がまし」と思えたことで、何とか踏ん張ることができました。過去の自分が頑張ってきたからこそ、今の困難にも立ち向かえる。それが、私にとって大きな支えでした。
ルーティンが見えてくると仕事は楽になる
1年を過ぎた頃から、業務の流れがつかめるようになり、気持ちにも時間にも少し余裕が生まれました。
年度ごとに教員の担当が変わり、毎年新しい研究費に向き合う必要はありますが、大まかな年間スケジュールは共通しています。
たとえば「この時期にはこの書類の提出があるから、1ヶ月前には準備しておこう」といった計画が立てられるようになり、効率も上がりました。
3年目になる頃には、処理スピードも向上し、仕事の量が増えても以前ほど大変に感じることはありませんでした。
会計業務で学んだ本質:「前提を揃える」ことの大切さ
この職場で特に学んだのは、「前提を揃えて説明する」ということの重要性です。
先生方は多忙なので、「で、どうすればいいの?」と結論を急ぐ傾向があります。しかし、前提条件を共有せずに答えだけを伝えると、誤解を生んだり、後で問題が起こったりすることがあります。
そのため私は、必ず背景や根拠を簡潔に伝えた上で、選択肢や最善策を提示するようにしました。
「なぜダメなのか」「どんなルールに基づいているのか」というエビデンスを示しながら、時には強く断ることも必要です。相手が教員であっても、ルールに反することは通せない。
そうしなければ、後で困るのは先生ご自身です。
この「厳しさ」は、決して冷たさではなく、「先生の研究を守る」という意識からくるものでした。
研究者が安心して研究に集中できる環境をつくる仕事
私の仕事の本質は、「先生が研究費のことで悩まずに、研究そのものに集中できる環境を整えること」でした。
予算の不備や不適切な処理によって、後で返金やトラブルに巻き込まれることがないよう、先回りして確認・指導を行う。
それが、私たち事務職員の役割です。
毎日忙しくても、先生から「ありがとう」「助かったよ」と言われた時には、「やっていてよかった」と心から思える仕事でした。