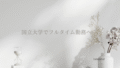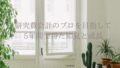国立大学での会計業務とは? 現場で見たリアルな仕事内容
配属されたのは、研究費を扱う専門部署
私が配属されたのは、大学の中でも研究費に特化した会計部署
配属されたのは、研究費を扱う専門部署私が配属されたのは、大学の中でも研究費に特化した会計部署。一般的な大学の経理とは異なり、外部資金(競争的研究費や共同研究費など)を適切に使うための管理と支援が主な仕事です。一般的な大学の会計業務とは少し異なり、「研究費の適正な執行」を支える、専門性の高いポジション。ここから、私の本格的な「大学職員としての実務スキル習得」の日々が始まりました。
担当教員ごとの研究費管理〜ルールは一つじゃない
この部署では、研究者一人ひとりに担当者がつき、獲得した外部資金の管理・執行を最初から最後まで支援します。私が担当したのは、外部資金を多く持つ教員が多く、科研費・共同研究費・受託研究費など、様々な種類の研究費を扱いました。
研究費には、それぞれに異なる規定やルールがあります。例えば、科研費には科研費のルール、企業からの共同研究費にはまた別のルールが適用されます。先生方は研究のプロではあっても、会計のルールには詳しくないことが多く、「任せたよ」と言われることもしばしば。
だからこそ、こちらの判断ミスが後に大きな問題につながる可能性もあります。もし不適切な支出があった場合、予算の返還が求められ、最悪は先生が自己負担で返金することに。責任の重さを感じながら、1件1件、慎重に仕事を進めていく必要がありました。
覚悟を決めて働いた日々が、確かな自信に変わった
当時はとにかく必死で、残業は月90時間を超え、土日も仕事、年末年始も資料を自宅に持ち帰って勉強しました。「家族には申し訳ないけど、今が頑張りどき」と腹をくくっていたことを覚えています。
この数ヶ月間の怒涛の経験を通して、「ルールを正しく解釈し、ミスなく処理する力」「前例を探して応用する力」「教えてもらうための準備力」など、今の私の土台となるスキルが一気に磨かれました。
補足
大学の「会計」といっても、研究費は特殊ルールがいっぱい
- 私が配属されたのは、大学の中でも研究費に特化した会計部署。一般的な大学の経理とは異なり、外部資金(競争的研究費や共同研究費など)を適切に使うための管理と支援が主な仕事です。
- 研究費ごとに異なるルールを把握して管理
- ひとことで「研究費」といっても、資金源ごとに使用ルールや報告の様式が異なります。そのルールを正しく理解していないと、最悪の場合、先生が個人で費用を返還することになります。
- 前例を探して、自力で答えを導く日々「前例を探す」ことから始まる仕事の進め方
- 大学では、すべてを丁寧に教えてくれる人はいません。「前に誰がどうやったか」を資料から探し出し、それを読み解きながら進めるスタイルです。自分から動けなければ、仕事にならない環境でした。
- 聞くときは“自分で調べたうえで”がルール
- 質問をするときは「ここまで調べたけど、ここがわかりません」と伝えるのが基本。そうでないと「調べましたか?」と返されてしまう。誰かが助けてくれる前提ではやっていけない職場でした。
1年目は怒涛の日々。休日返上で乗り切った
- 年末・年度末は繁忙期。残業90時間超も
- 私が着任した時期は年度末直前。予算の使用期限と報告業務が重なり、未経験の状態で一気に業務を覚える必要がありました。休日出勤・持ち帰り作業も重なり、残業は月90時間に。
- 家でも勉強。正月もマニュアルを読む日々
- 仕事が終わっても、家で各種研究費の規定を読み込み、使い方を理解する日々。お正月も、1人で研究費マニュアルを読んで過ごしました。
2年目・3年目でようやく見えてきた全体像
- 年の流れがわかると“段取り力”がつく
- 1年を通してのルーティンが理解できると、事前準備がしやすくなり、仕事が格段に楽になります。教員ごとに研究費は異なりますが、全体の流れは毎年ほぼ同じ。経験が武器になっていきました。
- 担当教員が変わるごとに新しい調整も必要
- 教員が異動・交代するたびに、新しい研究費のルールを把握し直す必要がありますが、それも慣れてくると対応が早くなります。
「前提を揃えること」の重要性を学んだ
- 先生の「どうすればいいの?」にすぐ答えないようにします。先生たちは結論だけを知りたがりますが、前提を理解していないと誤解を招きます。だからこそ「こういう条件だから、こうなります」という説明力が大切でした。
終わりに:研究を支える“縁の下の力持ち”として
- 大学の会計職員の仕事は、単なる経理ではありません。「先生が研究に集中できる環境をつくる」ことが一番の使命です。
- そのためには、細かなルールの把握・先回りの段取り・毅然とした対応力が必要です。
- 最初は苦しくても、やればやるほど、確実にスキルが積み上がっていく仕事でした。